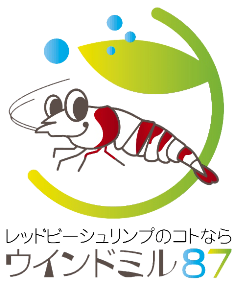2025/03/31 15:18
昔から水槽で魚を飼おうと思ったら、まずは水づくりからと言われてきました。
それは水を綺麗にするバクテリアを増やす事です。
(熱帯魚屋として飼育水の観点から、プランクトンや微生物も含めた肉眼で見えない生物の総称としてバクテリアと呼んでいます)

なぜバクテリアを増やす必要があるかというと、魚やエビは呼吸するときに鰓からアンモニアを出しています。
また、餌を食べるとタンパク質の多い糞をしますから、アミノ酸を経てアンモニアに変わります。(有機物分解菌の働き)
水中にアンモニアがあると呼吸しても血液が酸素を運び難くなり濃度が低くても時間が長引けば死んでしまいます。
そこで、アンモニアを分解するバクテリアにわいてもらい亜硝酸にしてもらいます。
亜硝酸もアンモニアほどではありませんが毒性がありますから亜硝酸を分解するバクテリアにわいてもらう必要があります。(硝化菌の働き)
現在のように生きたバクテリアという商品が無かったため、具体的に何をするかというと、水槽をセット(ろ過器や砂利や熱帯魚の場合はヒーターとサーモで温度設定)して水を張りすべての電源を入れ、すぐに魚を入れたいところですが、我慢して待つという行為です。
(魚がいない水槽で水だけ動かしているので「空回し」と言われています)
何を待っているかというと、魚が飼える程のバクテリアがわくのを待っているのですが、いつまで待てばよいのか具体的にはわかりませんので、おそらくもう大丈夫だろうと試験する意味で比較的安価な魚(テストフィッシュと言われます)を入れて様子見します。
もう少し積極的な方法として、最初から比較的安価な魚を少数購入し、餌を少量づつ与えアンモニアや亜硝酸を日々チェックし検出されなくなるまで待つという方法です。本命の魚を入れる前の水作りの為の魚なのでスタートフィッシュと呼ばれています。
テストフィッシュもスタートフィッシュもかわいそうという方は薬局でアンモニアを購入し、水槽に入れバクテリアがわいて硝酸塩になるまで待ちます。
ここまで「バクテリアがわくまで待つ」と言ってきましたが、実際には水槽内で新たな生命が誕生するはずがありません。
空気中の水分に菌類が入っていて、それらが水槽に入り、その中から条件(水温、PH、光、酸素、エネルギー源など)が合った菌類が繁殖するそうです。
なので「わく」というよりは「飛び込んでくる」の方が合っている気がします。
また、その菌類を常在菌というそうですが、どんな菌か?何種類か?割合は?というのは地域や場所で全く違う様です。
都合の良い常在菌がいる場所(海や河川や山など自然環境に恵まれた場所)なら待てば何とかなると思いますが、
公害の多い都心や工場地帯ではいくら待っても水を綺麗にするバクテリアが飛び込んでくれるとは限りません。
ですので、「空回し」から始まるむかしの水のつくり方だと、自然環境に恵まれた場所にお住いの人は「飼育がじょうず」と言われ、公害のある場所にお住まいの人は「飼育がヘタ」と言われます。ですが、引っ越しをすると「じょうずな人」が「ヘタ」になったり「ヘタな人」が「じょうず」になる場合もあります。
では、環境に恵まれない人(当店もそうですが)が水をつくるには バクテリア製品に頼る という方法があります。
ただし、バクテリアと書かれている製品ならどれでもいいわけではありません。製造メーカーや研究機関の話を聞いたり実際に何種類も試した結果、生きているバクテリア製品とうのはごくわずかだと思います。
しかも特徴もそれぞれ違いますから、ろ材やろ過器の選択で結果も変わってきます。
私の知る限りですが、生きているバクテリア製品は上記の3種類とその他にバイコムだけです。
以前はバイコムも販売していました。バイコム78硝化菌のアンモニアと亜硝酸の分解能力は凄まじいものがありますが、適正PHが7~8と弱アルカリ性で、下限は6で活動もかなり鈍くなるそうです。
当店のM87ソイルを使うとPH6以下になりますので相性が悪く、今は販売を見合わせています。